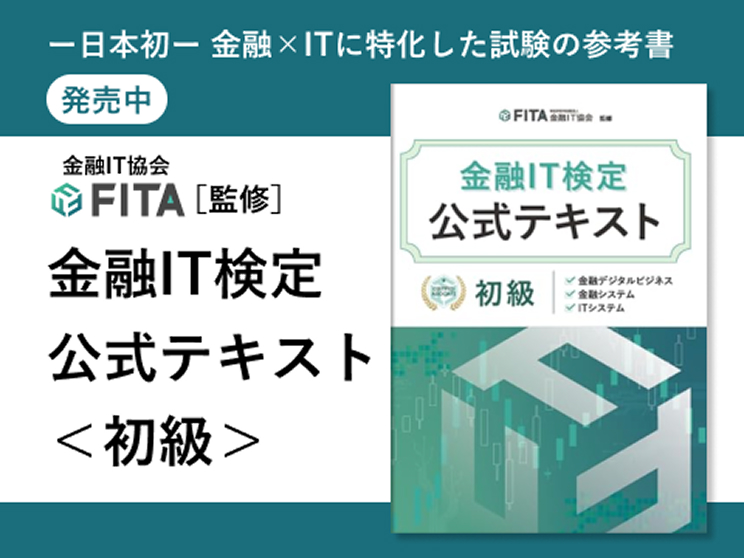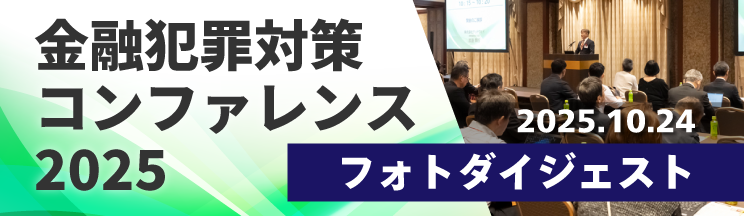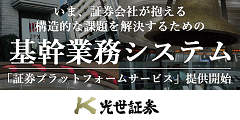取材レポート:金融・IT業界向け
2025.06.13
【グッドウェイ】生成AIと金融DXのリアルと展望を追う「金融AI EXPO2025」を開催!(午前の部)

2025年5月23日(金)、グッドウェイは「金融AI EXPO2025」を東京コンベンションホールにて開催した。本イベントは、金融業界の第一線で活躍する企業・専門家たちが一堂に会し、生成AIやデータ利活用の最新事例や展望を語る場として開かれた。


開幕の挨拶に立ったのは、岡田 拓郎 氏(金融データ活用推進協会(FDUA) 代表理事、金融IT協会(FITA) 副理事長、Trust 代表取締役CEO)。
本記事では、当日の基調講演やパネルディスカッション、表彰式を含む一連のセッションの内容を通して、金融業界における最新の取り組みと各社の実践事例をご紹介する。
| 特別講演 | 「AIと共に働く時代:チームを拡張するためのAIディスカッションペーパーの活用」 |

五十嵐 ほづえ氏(金融庁 総合政策局リスク分析総括課参事官)より、「AIと共に働く時代:チームを拡張するためのAIディスカッションペーパーの活用」と題した講演が行われた。
金融庁では、AI技術の進展にともない、現場での適切な活用を後押しする目的で、実務的な視点を盛り込んだ「AIディスカッションペーパー(ver.1.0)」を公開。人口減少に直面する日本社会において、AIは人材不足を補う存在として注目される一方、現場では「どう使えばいいかわからない」といった声も多く、実態に即した支援が求められている。
講演の中核となったのが、ディスカッションペーパーの概要だ。ペーパーでは、AI活用における課題を「従来型と生成AIに共通する課題」「生成AIによって難しくなった課題」「生成AIがもたらした新たな課題」の3つに分類。特にハルシネーションや説明責任の困難さ、外部とのコミュニケーションギャップといった実務上のリアルな課題が取り上げられた。
さらに、ペーパー作成の基となったアンケート調査等から、実際のユースケースや金融機関の取り組み事例も紹介。「ROI(投資対効果)が見えにくい中でも、KPIを工夫して運用を開始した」「グループ内にCoE(Center of Excellence)を設けて統制を図った」など、試行錯誤しながら実装を進める現場の知見が共有された。
| 講演 | 「Power Up Your AI:ニュースと生成AIを活用して競争優位性を獲得」 |

サチン・B・シン氏(ダウ・ジョーンズ アジア太平洋地域 エンタープライズソリューション責任者)は、「ニュースと生成AIの活用によるリスク予測とビジネス成長の可能性」と題して、同社が世界中のクライアントと共に実証してきたユースケースと仕組みを紹介した。
ダウ・ジョーンズは、生成AIの世界的な導入が加速する中で、ニュースメディアにおける著作権に関する課題を認識している。こうした状況に対応するため、同社のFactivaでは、生成AI向けに利用可能なコンテンツをまとめたフィードを提供していると説明した。
このフィードは、生成AIアプリケーションに特化した、グローバルかつ多様なライセンス取得済みニュースデータを取り揃えている。The Wall Street Journal や Barron’s、Financial News、Investors’ Business Daily などの高品質な媒体を多数含み、156カ国‧26言語にわたる網羅的なコンテンツが利用可能となっている。さらに、すべてのコンテンツにはメタデータが付与されており、さまざまなAI活用ユースケースにおいて柔軟かつ効果的に活用できる。
実際の活用例として、過去10年分のニュースデータを学習させた独自モデルによって、企業の経営危機や破綻を3〜6か月前に予測する仕組みを開発。リスクスコアの“スパイク”が与信格下げや倒産など重大イベントの予兆となっている事例を複数紹介し、実用性とROIの高さを強調した。
また、営業支援やESG評価、投資判断、業界特化型のインサイト提供など、生成AIとニュースを掛け合わせた多彩な活用事例も紹介。特に「カスタマイズされたニュースレター」「リアルタイムの対話型AIチャットボット」「即時生成の調査レポート」など、業務効率を飛躍的に高める具体的な仕組みが注目を集めた。

「金融機関のAI活用を支えるデータ基盤の革新力」と題し、砂川 俊明氏(SIXファイナンシャル インフォメーション ジャパン 日本法人副代表 営業部長)と、三本木 宏氏(Snowflake データクラウドプロダクト ストラテジックスペシャリスト)による対談講演が行われた。
| 講演 | 「金融機関のAI活用を支える“データ×基盤”の革新力」─SIX × Snowflake対談 |

「金融機関のAI活用を支えるデータ基盤の革新力」と題し、砂川 俊明氏(SIXファイナンシャル インフォメーション ジャパン 日本法人副代表 営業部長)と、三本木 宏氏(Snowflake データクラウドプロダクト ストラテジックスペシャリスト)による対談講演が行われた。
冒頭では、スイスに本拠を置くSIXグループの事業概要が紹介され、証券取引所の運営や金融情報サービスの提供など、多角的な金融インフラ事業を展開していることが語られた。特に、世界中の金融機関に対するデータ提供の実績が強調された。
本題となる対談では、まずSnowflakeのデータクラウドの特性が説明された。データのサイロ化や複雑な取り込み手順といった従来の課題を解消し、単一基盤上でセキュアかつ柔軟なデータ共有を実現する仕組みを紹介。また、マーケットプレイス機能により、金融・非金融を問わず多様なデータソースを容易に活用できる点も注目された。
金融業界における「信頼できるデータ」の重要性や、データ戦略なくしてAI戦略は成立しないという共通認識のもと、両者はデータの民主化とガバナンスの効いたコラボレーションの必要性を強調。SIX側からも、資産運用立国への流れを背景に、グローバルな視点から日本市場の可能性に期待が寄せられた。
| 特別パネル | 「保険業界における生成AIの進化と現場変革」 |

生成AIの業務活用が進む中、保険業界でも現場主導の変革が各社で加速している。本パネルでは、品川 輝氏(ニッセイ情報テクノロジー 執行役員 開発技術革新部長 販売チャネルソリューション事業部担当)、高橋 直子 氏(アフラック生命保険 AI・データアナリティクス部担当 執行役員)、木村 英智 氏(東京海上日動システムズ デジタルイノベーション本部 データ活用部長 シニアスペシャリスト(データサイエンススペシャリスト))の3名が登壇し、山口 省蔵 氏(金融IT協会(FITA) 理事長、熱い金融マン協会 代表)によるモデレーションのもと、生成AIに対する取り組みの全体像と現場の実践について語られた。
ニッセイ情報テクノロジーの品川輝氏は、システム開発の高度化を軸に、生成AIの活用を段階的に全社へ展開している体制を紹介。先行事業部でのPoC(実証実験)を経て、現在は社内全体でユースケース拡大を目指しているという。社内向けにはドキュメントやソースコードを素早く検索・可視化するアプリケーションを整備し、開発者の支援や設計・影響分析の効率化を実現。また、タグ変換やコード補完を通じてマイグレーション作業の自動化にも挑戦しており、既存システムの省力化にも生成AIを活用している。
アフラックの高橋直子氏は、「守り」と「攻め」の両面から生成AIの活用を進める態勢を紹介。AIリスク管理態勢を強化し、法務部など関係部署との連携を重視する一方で、営業支援・代理店業務・社内業務の3つの領域にわたってユースケースを展開している。社内では、社員が自由に生成AIを活用できる「Aflac Assist」を提供。営業支社からは、自主的にロールプレイングをプロンプト設計で行うなど、現場発の工夫が広がっており、好事例をコンテスト形式で横展開する取り組みも行われている。
東京海上日動システムズの木村英智氏は、社内でPoC(実証実験)を進める中で、生成AIの特性を活かすには従来のシステム開発とは異なる考え方が求められると指摘。PoCの段階で手応えがあっても、業務に展開するまでの壁は依然として大きいと語った。また、PoCが一過性に終わらず、社内に継続的な文化として根づくことが重要だと述べ、生成AI活用における風土づくりの必要性を強調した。
今回は2024年9月〜2025年3月までに実施された初年度試験の成績上位者が表彰対象となり、「金融IT検定 初級」試験(全60問・300点満点)の中で特に優秀なスコアを収めた受験者が壇上へと招かれた。
| ランチョンセッション | ~生成AI時代の人材育成~『金融IT検定 表彰式』 powered by FITA |

「生成AI時代の人材育成」として開催されたセッション内で、「第1回 金融IT検定・初級 表彰式 powered by FITA」が行われた。進行を務めたのは、中山 靖司氏(検定WG長、SBI金融経済研究所 統括主任研究員、SBI大学院大学 客員教授、金融IT協会(FITA) 理事)。プレゼンターとして、山口 省蔵氏(金融IT協会(FITA) 理事長、熱い金融マン協会 代表)が登壇した。
表彰式に先立ち、中山氏より金融IT検定の趣旨と仕組みについて紹介がなされた。金融業界におけるITリテラシーの底上げを目的とし、「金融×IT×ビジネス」を横断的に理解する人材の育成を目指すこの検定は、2024年9月に初回が実施されたばかり。対象者は金融機関の営業・事務・IT部門から、金融系システム会社の技術者まで幅広い。合格者にはSlackを活用した情報交換コミュニティ「CFIT」への参加権も与えられ、講演会・勉強会といった継続学習の機会が提供されている。
今回は2024年9月〜2025年3月までに実施された初年度試験の成績上位者が表彰対象となり、「金融IT検定 初級」試験(全60問・300点満点)の中で特に優秀なスコアを収めた受験者が壇上へと招かれた。
【協賛企業一覧(五十音順)】 【プラチナスポンサー】
アルテアエンジニアリング, SIXファイナンシャルインフォメーションジャパン, Snowflake Japan, セゾンテクノロジー, ダウ・ジョーンズ, Dataiku Japan, Trust,WorkX【シールバースポンサー】
伊藤忠テクノソリューションズ, TRUSTART, PKSHA Communication, ベリントシステムズジャパン【後援】
金融IT協会、金融データ活用推進協会
アルテアエンジニアリング, SIXファイナンシャルインフォメーションジャパン, Snowflake Japan, セゾンテクノロジー, ダウ・ジョーンズ, Dataiku Japan, Trust,WorkX【シールバースポンサー】
伊藤忠テクノソリューションズ, TRUSTART, PKSHA Communication, ベリントシステムズジャパン【後援】
金融IT協会、金融データ活用推進協会
(取材、撮影、記事、編集・制作 : GoodWayメディアプロモーション事業部 @株式会社グッドウェイ )
![]()
レポート
-

取材レポート:金融・IT業界向け
2025.12.12
【グッドウェイ、セミナーインフォ】金融 IT EXPO 2025開催~生成AI時代の システムモダナイゼーションと サイバーセキュリティ対策~【後編】
-

取材レポート:金融・IT業界向け
2025.12.11
【グッドウェイ、セミナーインフォ】金融 IT EXPO 2025開催~生成AI時代の システムモダナイゼーションと サイバーセキュリティ対策~【中編】
-

取材レポート:金融・IT業界向け
2025.12.10
【グッドウェイ、セミナーインフォ】金融 IT EXPO 2025開催~生成AI時代の システムモダナイゼーションと サイバーセキュリティ対策~【前編】