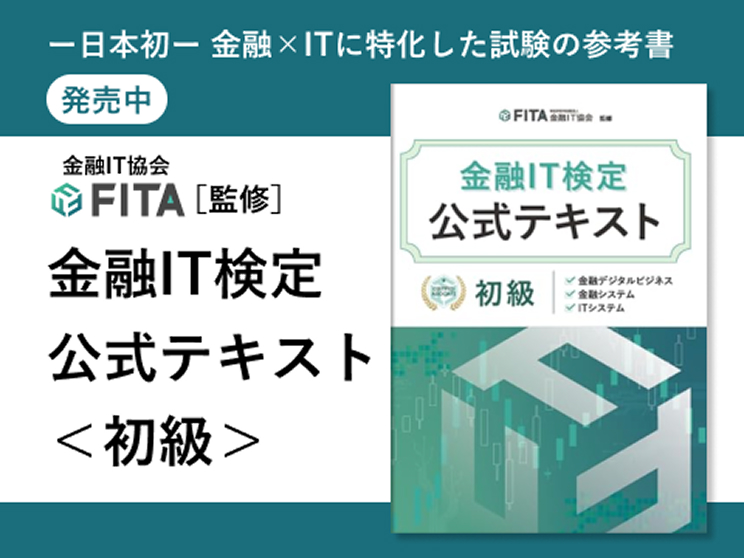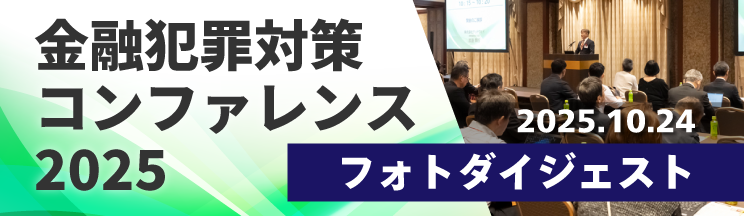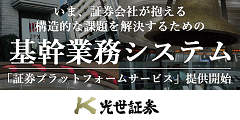金融
2025.11.05
金融×AIで業界の垣根を超える!FDUAの岡田代表理事が語る「人をアップデートする使命」:後編

後編:FDUAの挑戦と未来 〜金融の枠を越え、人をアップデートする挑戦〜
(前編の続き)
七十七銀行・全銀協・三菱UFJ信託銀行を経て、岡田代表理事が構想した“業界横断コミュニティ”。その思いが具体的な形となったのが、金融データ活用推進協会(FDUA)です。ここから、FDUA設立の経緯と今後の展望を伺います。
- プロフィール
-
- 岡田 拓郎
- 金融データ活用推進協会(FDUA) 代表理事
- 東北大学工学部卒業。 七十七銀行、全国銀行協会、三菱UFJ信託銀行、デジタル庁で一貫して金融
デジタル分野に従事。2022年 金融データ活用推進協会(FDUA)を設立(理事長)、NPO法人金融IT協会(FITA)を立上げ(副理事長)。
[金融データ活用推進協会(FDUA) 代表理事 岡田 拓郎]

後編:FDUAの挑戦と未来 〜金融の枠を越え、人をアップデートする挑戦〜
(前編の続き)
七十七銀行・全銀協・三菱UFJ信託銀行を経て、岡田代表理事が構想した“業界横断コミュニティ”。その思いが具体的な形となったのが、金融データ活用推進協会(FDUA)です。ここから、FDUA設立の経緯と今後の展望を伺います。
「だからこそ腹を割って話せる“横串”の金融コミュニティがあれば、各社の可能性はもっと広がるはずだ」と確信しました。ちょうど私が三菱UFJ信託銀行でAIやFinTechの企画担当となり、最新技術に取り組む中で横のつながりの重要性をさらに実感する出来事がありました。未知の技術テーマではベンダーやコンサルから情報収集をしても限界があり、一度同じ金融機関の立場の仲間と腹を割って話す方がよほど有意義だったのです。
そこで社内の有志や他社の仲間に声をかけ、三菱UFJ信託銀行のオフィスで「金融事業 × 人工知能コミュニティ」を立ち上げました。FDUAの理事でもあるSBIの佐藤市雄さんなど、みずほ、三井住友の中心的な方に参加いただき、皆で集まって議論しました。確かな意義を感じましたが、当時(2020年頃)はAIが今ほど注目されておらず、金融界でも日陰の取り組みでした。ブロックチェーンやメタバースが流行り、その前は決済APIブーム。AIは「儲からないし効果も不透明」と冷ややかに見られ、「やらなくてもいいじゃないか」と言われる時代です。それでも私は「AIの時代は必ず来る」と信じていました。経営層からROI(投資対効果)の低さを指摘され続けても、「いつか僕らの時代が来る」と信じ、今だからこそ横のつながりを作り、コミュニティ活動を継続しようと仲間たちに呼びかけていきました。
――それをFDUAに昇華させたきっかけ・経緯を教えて下さい。
社内コミュニティを続けるうちに、会社の枠組みの限界も見えてきました。いくら横のネットワークを広げても、所詮「三菱UFJ信託銀行の立場」ではMUFGグループの外には出られません。信託銀行という業態の枠もあります。もっと大きな社会課題を解決しようと思うなら、自ら環境を変えて“川上”に行くしかない——それが私の考え方でした。組織の環境は重要で、自社の枠内にいては越えられない壁があると痛感しました。 ちょうどその時期、「デジタル庁」が新設されるという話を聞きました。人材募集もしている。「ここだ」と直感しましたね。社内コミュニティをいっそ社団法人に昇華し、業界全体を巻き込むプラットフォームにしよう——そう決意してデジタル庁に飛び込みました。
私の尊敬する坂本龍馬も土佐藩に安住せず、命がけで脱藩して京都・江戸へと飛び出した人物です。龍馬は「これをやりたい」という具体的な内容までは当時なかったかもしれません。それでも「信念を持って、まず行動する」ことを大事にしていたのではないかと思います。私もまずは自分が川上へ行ってみよう、と。実際に行ってみた場所にこそ、自分が解決すべき課題が転がっていて、それを自分で掴み取って解決すべきではないか——そう考えたんです。確たる正解があるわけではありませんでしたが、コミュニティを社団法人に切り替え、業界全体を仕切る“段取り役”になれるだろうと期待し、デジタル庁への転身を決めました。

FDUAは「業界横断で非競争領域を作ること」「個人が活躍できること」を目指す
――デジタル庁では、自分の思い通りに進みましたか?
正直、紆余曲折だらけで大変なことも多かったです。
ただデジタル庁に入ったことで官公庁の知り合いが一気に増えました。そして何にも増してデジタル庁で学んだことは、「主語が常に日本」であることです。民間企業にいると自社をどうするか、自部署をどうするかでしたので、視座が上がる気はしました。デジタル庁で働いている人は皆、常に日本をどうするか言うことを考えている。自分も気持ちが高揚し、社団法人にして、そこから業界活動を本格的に広げていこうと決意を新たにしました。
――FDUAを作る際、どのような組織にしようと考えましたか?
立ち上げにあたって念頭に置いたのは2点です。
1つめは業界横断で非競争領域を作ること。
2つめは個人が活躍できること。
「金融データで人と組織をアップデートしよう」というビジョンを掲げました。
当時まだAIは傍流でしたが、やっていることは可能性があるし、横のつながりをつくっていくことで、その人自身も輝ける。働いていて面白いということを加速させたい。それゆえに「データ」より「人」という言葉を前に置いて強調しました。 幕末の坂本龍馬が薩長同盟を実現させた裏には、彼自身の卓越した能力というより“人と人とをつなぐ行動力”があったのではと私は思っています。だからこそ藩を超えた同盟を組み、「一緒にやった方が自分たちのためになる」と周囲に思わせることができたのではないでしょうか。私自身も決して一人で何でもできるスキルフルな人間ではありません。でもFDUAには各領域に精通した素晴らしい理事の方々が集い、理念に共感した会員企業にも優秀な人材が集まってくださった。そのおかげで今、一定の成果を上げられているのだと思います。
――一般的に閉鎖的と言われる金融機関を巻き込むのは大変だったと思いますが。
はい、最初はかなり苦労しました。まずは金融業界を代表する方に理事になって頂きたいという想いで、Japan Digital Designの河合さん(現高知銀行頭取)にお声掛けし、その場でご快諾を頂いたこと今でも記憶に新しいです。河合さんには、当初何もなかったFDUAに参画頂いた事に本当に感謝しています。
その後、SBIの佐藤さんと一緒に各社を廻っていきました。時には、反対されたり、協力を得られなかったりもたくさんありました。「何がやりたいのかよくわからない」と言われ、めげそうになったこともあります。 しかし、良い意味での“鈍感力”があって(笑)、1度断られても、また時期を見て誘えばよいと気持ちを切り替えました。創設時からいる仲間たちとともに諦めず各社を回り続け、少しずつ輪を広げていきました。
――金融機関以外の特別会員にも協力いただいていますね。
金融機関だけだと技術力が足りません。金融機関にいる人だからこその金融AIのノウハウやメソッドがある一方で、社内調整とか社内対応にリソースをさかざるをえない。技術的アプローチ、法律的アプローチが十分ではないので、ベンダー企業、Sier、コンサル、法律事務所などの特別会員の力を借りて、一緒に進めないと本当に良いものは生み出せないと思っています。
業界の非競争領域で社会実装を増やしていく
――5年後、10年後はどのようになっていると思いますか?どのように進みたいですか?
正直、5年後、10年後がどうなっているかはわかりません。3年前にFDUAを立ち上げた当初も3年後の姿を予想できませんでした。ですから5年後を問われても「どうなっていても大丈夫なようにしておく」くらいしか言えません。AIの進化スピードはあまりに速く、未来予測が難しい面もあります。だからこそ「今やれること」を毎日全力でやり続けるのみです。
ただしFDUAとして「業界横断で課題を解決していく」「人をアップデートしていく」ことは5年、10年たっても変わっていかない。ここはぶれさせずに日々愚直にやり抜くことだと思っています。
――FDUA発展に向けて、ご自身はどのようなスキルアップをしていますでしょうか?
お恥ずかしながら、最近は自分のスキル磨きがおろそかです。できるだけAIツールを触ったり、開発したり、したいのですが。その代わりといってはなんですが、ここ最近は地政学への関心が高まっています。 というのもFDUAはいまだ大きな社会課題を解決できておらず、これから業界にインパクトを与えていくにはどうすべきか考えた時、歴史が動いた瞬間に興味を持つようになったんです。「なぜその時その組織は動いたのか?動くモチベーションは何だったのか?」と。そう考えていくと歴史や地理の必然性に行き当たり、その前提となる地政学こそ組織が動く大きな変数だと最近学びました。技術知識だけでなくこうしたことまで学んでみよう——そう思っています。明確な答えがあるわけではありませんが、大きな社会インパクトを起こす共通点を探るヒントが得られるかもしれない、と感じています。
――直近で、FDUAとしてこれをやっていきたいということを教えて下さい。
これまでを振り返ると、当初やりたかったことは実現できたと思います。
中でも一番やりたかったことは、データコンペティション。これは自分の中では一丁目一番地でした。人材をアップデートする、つまり業界横断で埋もれた人材を発掘する仕組みを作りたかったんです。
実は私自身、銀行の営業店にいた頃は全然仕事ができない行員でした。新しいことをやりたいのに窓口業務では適性が活かせず、「銀行員に向いていないな…」と悩んだものです。でも銀行にはAIやテクノロジーが得意な人、他の業務で才能を発揮できる人がきっと大勢いる。特に地域金融機関には地元に埋もれた優秀な人材がたくさんいるはずです。にもかかわらず、そうした高いポテンシャルを持つ人を見つけ出し続ける仕組みがこれまで業界にはありませんでした。だから私は業界横断でデータ分析コンペを開催し、「こんな凄い人がいる!」と業界全体で表彰・称賛する場を作りたかった。そして受賞者が適材適所に人事異動して活躍できるようになる——そんな人材アップデートのサイクルを生み出したかったんです。実際、データコンペティションはFDUA設立後に開催でき、私たちがやりたかったことの一つを形にできました。
逆にやれてないこと、それはもう少し具体的な、社会実装に近いことをやっていくことです。「金融生成AIガイドラインづくり」、「金融AI成功パターン出版」はすごく意義があることで、どちらも金融機関の方々から感謝の言葉をいただいており、その声を聞くと本当にうれしいです。
しかし本当の意味で社会的インパクトを起こすとなると、より実装の方に近づいていくというのをやらないといけない。やっていくことがFDUAの存在意義を高めることになると思っています。
今現在では、金融業界横断データ連携プラットフォーム。複数金融機関がデータを秘密計算という手法で、疑似的に共有する、そこから粉飾検知をする、というPoCに着手しようとしています。これは業界横断の非競争領域で、実装に近い話ですね。こういう業界非競争領域の社会実装を協会の中で増やしていきたいです。
――AIエージェントではどのような活動を想定されていますか?
AIエージェントは、今、各金融機関などが懸命に取り組んでいるところです。例えば、対顧客向けAIガードレールの作り方、セキュリティのあり方、AIガバナンスなど、こういうところでも非競争領域が起きるはずです。「金融生成AIガイドライン」も2025年6月にアップデートしました。さらに踏み込んだ、より実装に近いところをまとめていきたいと思っています。 具体的には、実務で使えるプロンプト(AIへの指示文)やプログラムレベルのノウハウなど、実装可能なレシピを業界で共有していくイメージです。地方の中小金融機関でも自前のリソースでAIエージェントを作り、金融サービスの高度化につなげられる——そんな未来を目指し、業界横断の取り組みに発展させていきたいと思います。
――現在のAI活用はリテールビジネスのフロント領域に偏っている印象があります。ミドル・バックオフィス業務への活用も可能でしょうか? その問いはまさにモダナイゼーションの話につながります。現状、金融機関の基幹システム自体がサイロ化(縦割り)されていて、その上にAIエージェントを載せようとしても限界があります。本質的には金融機関のレガシーシステムをモダナイゼーションし、そのうえで生成AIを活用することが近道だと考えています。私自身これまでマーケティングや市場予測分析といったフロント領域のAI活用を中心に手掛けてきましたが、それだけでは限界を感じました。企画部門など一部ホワイトカラーの効率化に留まってはインパクトが小さいんです。金融機関職員の8割は事務を担う現場です。ですからまずはレガシーシステム脱却が先決でしょう。ITコンサルタントや社内外のAIデータサイエンティストが一丸となって、金融の基幹系を現代化し、その上で生成AIをフル活用する。それが遠回りに見えて実は王道だと思います。
全ての金融コミュニティをつなげていく
――金融業界を盛り上げていくために、後輩に向けて伝えたいことはありますか。
私などまだ後進に偉そうに語れる立場ではないかもしれませんが…(笑)。それでも一言で言えば、金融業界は今も十分面白いし、これから先もっと面白くなると信じています。金融には社会への大きなインパクトを与える力がありますし、だからこそ金融以外の分野で活躍している人にもぜひ業界に飛び込んできてほしいんです。金融にしかできないことが山ほどあります。一緒に金融を面白くする仕事に携わってもらえたら本当に嬉しいですね。ぜひ私と一緒に、業界横断で新しいことに挑戦していきましょう。

(聞き手:グッドウェイ 取締役副社長 渡邊 素行)