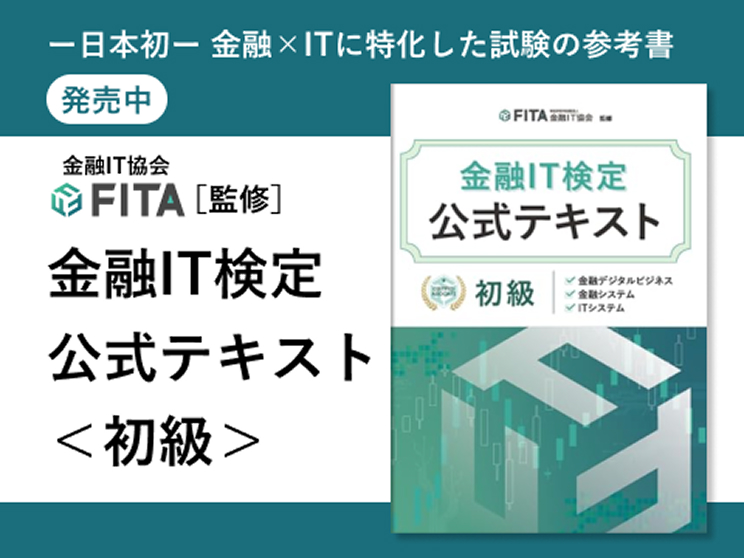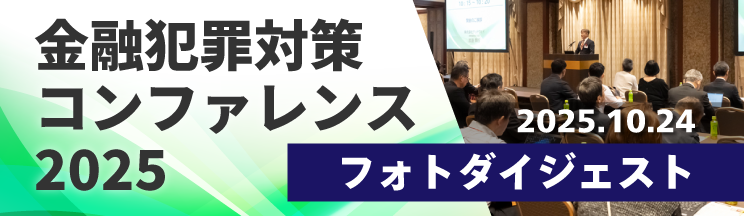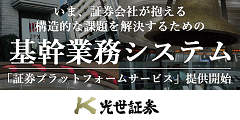金融
2025.10.31
金融×AIで業界の垣根を超える!FDUAの岡田代表理事が語る「人をアップデートする使命」:前編

前編:原点と使命 〜銀行員としての経験が導いた社会課題解決への道〜
AI技術が凄まじい勢いで進化していく中、その金融での活用が模索されています。金融データ活用推進協会(FDUA)を設立した岡田代表理事に協会設立の経緯・目的、今後の方向性などを伺いました。
- プロフィール
-
- 岡田 拓郎
- 金融データ活用推進協会(FDUA) 代表理事
- 金融業界横断でAI・IT活用を推進することをミッションに複数団体を運営。
銀行ではAI・データ活用組織の立上、スタートアップアライアンスを所管。
2022年 金融データ活用推進協会を設立、NPO法人金融IT協会を立上げ。
2023年 金融AI・ITでビジネス効果を最大化するスタートアップTrust㈱を設立。
[金融データ活用推進協会(FDUA) 代表理事 岡田 拓郎]

前編:原点と使命 〜銀行員としての経験が導いた社会課題解決への道〜
AI技術が凄まじい勢いで進化していく中、その金融での活用が模索されています。金融データ活用推進協会(FDUA)を設立した岡田代表理事に協会設立の経緯・目的、今後の方向性などを伺いました。
地震を研究していた学生が金融業界に
――銀行に就職した経緯を教えてください。
神奈川県横浜市出身ですが、人と同じことをしたくなかったので、東京以外の大学として東北大学を選択し、大学では社会環境工学科(土木)を専攻、地震の研究をしていました。
実家は土木会社を経営していて、当時はそれを継ぎたいという思いがありましたし、国交省やスーパーゼネコンに行ってエリートになるという道も考えました。それが親孝行につながると思っていました。
卒業論文では、大間の原子力発電所に経産省が認可を下ろしてよいかどうかについて、自分の研究成果が認可の1つの材料になるということだったのでやりがいを感じていました。一方で自分は研究者向きではないな、とも思っていました。
むしろ都市経済の方が面白いかと。生身の経済であり、特に金融は都市経済に近いので。
仙台に住んでいたこともあり、仙台の地銀として七十七銀行を選択しました。あまり深く考えた就職ではなかったと思っています。
――銀行での仕事はいかがでしたか。
最初は松島支店配属され、窓口補助を担当しました。
この伝票を処理してくれ、再鑑してくれ、と言われても、「それはどういう目的なのですか?」「なぜシステム化されていないのですか?」と聞いてしまうタイプ。「理系あるあるタイプ」「言われたことをやらないヤツ」ですね。
支店の業務になじめないし、理系なので、同期で最も早く半年でシステム部に異動。
当時は左遷されたというイメージでしたが、ITの方が向いてそうとも思いました。ただ銀行員として法人融資業務を1回はやりたかった。そこに心残りはあります。
システム部では、為替・決済・口座振替などを担当。自分が作ったシステムで宮城県内のかなりの部分の決済を動かす、県を動かしているという体験を通じて、モノづくりが面白くなり、仕事に没入できるようになりました。 結果、七十七銀行では、支店半年、システム4年、合計4年半の銀行員生活を送りました。

転機になった東日本大震災の被災
――七十七銀行から転職しようと思った経緯を教えてください。
大きな転機になったのは2011年の東日本大震災でした。当時、銀行の同期が亡くなるなど身近で被害が起き、「自分は何のために生きているのか。真剣に生きねばならない」と強く胸に刻みました。この経験で仕事への姿勢に火が付いたのだと思います。
震災当時、私は第6次全銀システムのプロジェクトリーダーでした。出先で被災し、信号が止まり、水道管が破裂する混乱の中を車で必死に銀行へ戻り、しばらくは乾パンでしのぎながら、泊まり込みでシステム障害対応にあたりました。つらいと感じることはなく、「何としても銀行のシステムを止めてはいけない」という一心で働き抜き、結果として全銀システムは止まりませんでした。
震災から半年ほど経ち、日常が戻りかけた頃、このままではまた別の場所で同じことが起きてしまうのでは、と感じるようになりました。自分の経験を他の場所で活かせないか、同じような被害を繰り返さない方法はないかと考えたのです。
そのような折、銀行の同じ寮にいた先輩が出社できなくなりました。その先輩が担当する取引先の社長が自ら命を絶ったと聞きました。津波で家族も工場も流され、家族の写真も流され、現金や手形、小切手さえも残っていなかったようです。「それらが少しでも手元に残っていれば再起する気になれたかもしれないのに、それすら無かった」と伺いました。
現金や小切手などの価値の証を少しでも残すことができれば、その社長は救われただろうし、今後も他の地域で同じような災害が起きても同じ結果にはならないはずだと痛感しました。自分はたまたま生き残ったのだから、この経験を活かして「なくならない仕組み」を作るべきだと使命感に駆られました。
ちょうどその頃、全銀システム担当という縁もあり、全国銀行協会(全銀協)のホームページで「でんさいネット※」のシステム担当の募集を見つけたんです。まさに「これだ!」と思いました。応募要件は「金融機関で決済システムを担当した経験がある人」「BCP(災害対策)ができる人」——まさに自分にピッタリでした。すぐ応募して、全銀協への転職を決め、「でんさいネット」のプロジェクト担当になりました。
※でんさいネット:全銀協傘下で運営する電子記録債権(電子手形)の決済ネットワーク
――なぜ全銀協から三菱UFJ信託銀行に転職したのでしょうか?
全銀協での仕事はやりがいがあり、人にも恵まれていました。しかし一方で業界全体を抜本的に変えるには限界を感じてもいました。全銀協自身が主体的に変革する意思を持ちづらい組織でもあり、業界の意思決定はいつも政府の法改正や監督方針、メガバンクの意向など「上から順に川下へ流れていく」構造なのです。つまり業界や社会の最上流(川上)に行かなければ、自分が感じる課題を解決できないと悟りました。「社会のためになる何かを成し遂げたい」と本気で思うなら、もっと上流に行く必要がある——そう気づいたのです。
では“川上”とはどこか。極端に言えば国会議員、ひいては総理大臣を目指すことかもしれない。実際、地元の有力者の誘いで議員秘書となり、政治の世界で上を目指す道も模索しました。しかし、資金集めや票集めに奔走する日々は自分の性分に合わず、短期間で秘書を辞めて政治家の道も断念しました。もう一度民間に戻り、自分の得意な金融やITの分野で働き直そうと決めました。 民間に戻るにしても「どうせなら業界の大きな舞台で挑戦したい」と考えました。ただ銀行に戻るとまたピラミッド組織の下層からになりかねない。自分の理想とする川上には行けそうにありません。そこで縁あって三菱UFJ信託銀行への転職を検討しました。面接で感じた社風はフラットで、組織規模も大きすぎず裁量もありそうだと好印象で、最終的に三菱UFJ信託銀行で働くことを選びました。
単一銀行ベースの金融コミュニティに限界を感じて、FDUA設立を構想
――金融コミュニティの立ち上げの経緯を教えてください。
三菱UFJ信託銀行では最初リスク管理を担当しました。もともとBCPやシステムリスクの畑でしたし、グループ初のAWSクラウド導入案件では、リスク評価を任されたこともあります。その在職中、実は密かにFDUAを立ち上げる構想を温めていました。きっかけは全銀協時代に感じた“業界横断のコミュニティ不足”への問題意識です。例えば全銀協で全国400行規模の説明会を開いても、終了後に参加者同士が名刺交換すらせず即座に帰ってしまうのが常でした。本来は皆同じような課題に向き合っているはずなので、その場で横につながりを作っておけば、いざという時に助け合えるのに…と歯がゆかったんです。同じ全銀システムを扱う者同士、課題も答えも各行ほぼ共通のはずなのに、当時は他行と気軽に相談し合う習慣がありませんでした。本当に切羽詰まった時だけ個別に連絡する程度で、業界の縦割りの強さを痛感しました。
「同じような課題を抱える仲間が横につながれば、もっと大きな変化を起こせるはずだ。」

次回(後編)では、この思いを形にしたFDUA設立の舞台裏と、岡田代表理事が描く“金融×AIの未来”について伺います。
(聞き手:グッドウェイ 取締役副社長 渡邊 素行)